過剰広告が生み出したTikTok「正直レビュー界隈」
最近、TikTokで急増しているジャンルがあります。
それが、「正直レビュー界隈」と呼ばれる投稿群です。
●パッケージの華やかさに対して「これは正直、微妙だった」
●人気商品に「SNSでバズってるけど、私はリピなし」
●案件動画に見せかけて「提供ではありません。本音です」と始まる動画
飲食店や化粧品、ガジェットなどを題材に、こうした“本音ベース”のレビュー動画が、着実にフォロワーを増やしています。
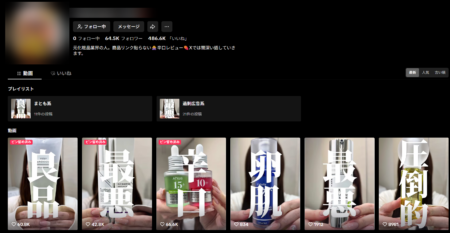
「案件くさい」ことへの拒否感
このブームの背景には、広告とユーザーとの信頼関係の揺らぎがあります。
TikTokがインフルエンサーマーケティングの主戦場になるにつれ、タイアップや案件投稿は急増。見た目は日常の動画でも、実は企業案件ということが多くなり、「これって本当に本音なの?」という疑念を抱く視聴者が増えています。
そこに登場したのが、“正直レビュー”系の投稿です。企業からの提供を受けずに自腹で購入し、「本当に使ってみてどうだったのか?」を忖度なく語るスタイルが、フォロワーとの信頼関係を築き、再生数や保存数、コメント数の増加にもつながっています。
「広告でよく見る」へのカウンター
たとえば、「この商品、過剰広告でした」から始まる化粧品のレビュー投稿。実際に使ってみた感想として「特に変化は感じなかった」「香りが強すぎた」などの率直な意見や、広告が薬機法に抵触しているのではと指摘する内容も見られます。
TikTok上でよく見かける広告商品を“あえてレビューする”という構図が、「ちょうど気になっていた」「あの広告、過剰だと思ってた」といった視聴者の共感と信頼を呼び起こしているのです。
「正直レビュー系アカウント」に寄せられる案件依頼
最近では、企業側も「ひたすら褒めるだけの案件」よりも、リアルに使ったレビューとして自然に見える投稿を重視する傾向にあります。
実際に、正直レビュー系アカウントにも企業からの案件依頼が増えており、その際の依頼内容も次のように変化しています。
●「良かった点と、微妙だった点の両方を話してください」
●「他社商品との比較もOKです」
●「“あえてリピートはしないかも”といったコメントも歓迎です」
このように、あくまでフラットな目線でレビューを依頼することで、視聴者からの信頼を損なわずに案件を成立させる工夫がなされています。
正直レビューも信頼できなくなり……
とはいえ、正直レビューにも課題はあります。本当に「正直」なのかを見極めるのが難しくなってきているのです。「正直なレビューであること」がひとつのブランド価値となった今、その“正直さ”を装ったアカウントも大量に増えていることで、「正直レビュー」への信頼も薄れてきているのが現状です。ご多分に漏れず、こういったマーケティングの手法はイタチゴッコになりますね。
直近の広告運用で起きていること
弊社も広告代理店として様々なパターンの広告を運用していますが、30代以上は「広告っぽい広告」でも問題なくコンバージョンが取れるのに対し、20代以下は「UGCっぽい要素」を加えないとコンバージョンが取れない傾向があります。
デジタルネイティブ世代にとって「WEBの広告が騙してくる」のは当たり前で、信頼してもらうためには嘘がないコミュニケーションが必要になるのでしょう。
ここから先、Z世代が30代40代になり購買力を強めていく中で「広告に簡単に反応してくれない」ユーザーが増えていきます。ネット販売においては、より正直な運営をすることが売上に繋がります。
「ユーザーには常に見透かされる」ということを、肝に銘じていきたいと思う次第です。

JECCICA客員講師 矢崎 宏一郎
(株)ISSUN チーフマネージャー
得意分野/WEB広告 EC販売支援
WEB広告のなかでもAI系広告を得意とし、事業規模に合わせた集客戦略でD2Cの売上を2年で10倍にするなどで、日本上位3%の代理店であるGoogle Premier Partner認定に貢献。
