消費者に対して悪質性のあるアプローチ!? 2025年から始まるダークパターン規制とは?
新年おめでとうございます。
本年も皆様のますますのご繁盛をお祈りいたします。
皆さんは年末の買い出しはどこに行かれましたか?よく東京の年末の風景として、御徒町のアメ横が撮影されますが、アメ横は、騙す・騙されるを楽しみながら買い物をする場でもありますよね。365日いつ行っても「本日をもって閉店。ブランドや値札に関わらず全品5,000円」と連呼するカバン屋や、「1万円の筋子が今日だけ1,000円、このクロマグロも今日だけ1,000円だよ~」と塩辛声を響かせる魚屋。
どちらも今日だけの特別価格ではないことは周知の事実で、定価もブランド表示も、何もかもが消費者を欺くものである可能性をはらんでいますが、アメ横で買い物する人はこれを楽しみに訪れているのであり、1,000円で買ったマグロが筋だらけで可食部が少なくても、5,000円で買ったスーツケースが帰宅するまでに車輪がなくなったとしても「そういうもの」として買い物を楽しんでいると言えるでしょう。
こういった消費者へのアプローチは、アメ横ではエンターテイメント性を含んでいるのに対し、EC業界ではエンタメどころか悪質性が深刻といわれ、被害者に関するニュースはよく耳にされるのではないでしょうか。
そこで今後、消費者に対して悪質性のあるアプローチは「ダークパターン」として注意対象となるとされ、2025年からは専門機関による評価制度が始まります。
ダークパターン規制と法的効果
言うまでもなく「〇〇病が治る」のような偏った情報の提供はそもそも薬機法で規制されており、ダークパターンではなく違法です。
一方、「今から10分間だけ利用できる特別クーポン」という残り時間カウントダウン表示のLPが出て焦って購入したのに、再アクセス時も同じクーポンが表示されて「もっとゆっくり比較検討できていれば買わなかったのに!」と消費者に後悔させることは、違法でないとしても許されることなのでしょうか。
ここ数年、ECやWEBでのホテル予約などインターネット経由での消費が一般化していくにつれて、ダークパターンが原因で消費者が金銭の損失を得たと申告する数が増えています。金額で換算しても、日本国内で年間1兆円を超える経済的被害が発生していると推定されています。
このような状況を受け、弁護士などの有識者たちが集まり、消費者庁や経済産業省などと連携して「一般社団法人ダークパターン対策協会」を設立し、企業の倫理的なデザインを促進するための評価制度、すなわち、各WEBサイトが非ダークパターンであることを認定する制度が開始することとなりました。
既存の規制だけではグレーゾーンとなりがちな範囲のうち、消費者が選びたくなかった選択肢を選ばせる手法や、解約に必要な情報に容易にアプローチさせない仕組みなど、消費者が気付かない間に不利な判断・意思決定をしてしまうよう誘導する仕組みはダークパターンと呼ばれ、今後EC業界では注意すべき指針が設けられる見込みです。
ダークパターンとして規制されるもの
上述の通り、ダークパターンは、既存の規制ではグレーゾーンな範囲から線引きすることになるため、何がダークパターンなのか明確な列挙は容易ではありません。そのため、消費者庁は2024年12月現在大原則と分類例を下記のように示しています。
<大原則>
●消費者に誤認や困惑を生じさせ
●それがなければしなかったであろう行為を消費者にさせるために
●技術や技法を用いているもの
<分類例>
①強制
ユーザ登録を強制すること。必要のない個人情報の開示の強制すること
例:商品を購入する際、特に商品とは関連のない範囲の個人情報まで登録しないと購入できない仕組み
②インターフェース干渉
事業者に有利な選択時を事前選択、協調していること
例:商品購入時に最初から「定期購入を希望」が選択されている。またはその選択肢が選択済みであること明確に見えるようになっていないUI
③執拗な繰り返し(ナギング)
何回も同じやりとりをすること
例:事業者からの通知や位置情報取得を許可していない消費者に対し、何度も「通知をONにします」「位置情報をONにします」等と誘い続ける方法
④妨害
解約やプライバシー保護を強化する設定への変更を難しくさせること
例:定期購入を解約したい消費者に対して、解約方法を明記しなかったり、容易に解約できないできない仕組みを設けて解約を妨害する方法
⑤こっそり(スニーキング)
取引の最後に急に料金が追加されて合計価格が変わること、および、トライアル期間後に自動的に定期購入になっていること
例:取引検討中には一切記載がなかった手数料などが、精算時に勝手に加算され、検討時に表示されていた金額と請求金額が変わっているケース
⑥社会的証明
他の消費者の行動について虚偽または不正確な通知を行うこと
⑦緊急性
虚偽の時間的制限や量的制限を表現すること
例:「今、〇〇人がこのサイトを見ています!」や「現在の在庫は〇個、お急ぎください」と虚偽の数字により焦らせる手法
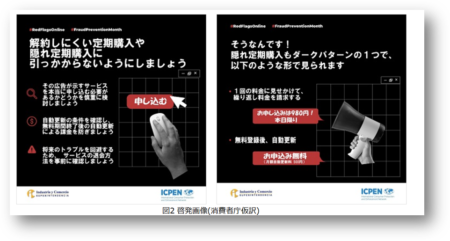
参照:消費者庁 www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_research/international_affairs/icpen_2023/
実はあのサイトもあのサイトも規制対象?!
「お試しセットを申し込んだら定期購入になっていた」「解約方法が複雑で解約不可能に近い」などのトラブルは以前から問題になっていますが、①の「必要のない個人情報の強制」というのは、実は複数のECサイトで見られるUIデザインではないでしょうか?
ECがD2Cのならではの恩恵として、ユーザ属性を握ることができるというメリットがありますが、日常的な消耗品を買うだけの消費者に対し、年収や家族情報などの過剰なヒアリングが購入の必要条件となっている場合、今後ダークパターンとして判断されてしまう可能性もあるかもしれません。
ダークパターンに関連する認定制度
一般社団法人ダークパターン対策協会では今後、各WEBサイト・ECサイトがダークパターンに該当しない「非ダークパターンである(=「NDD」)ことを認定する制度」を下記スケジュールで進めていくと公表しています。
2025年01月 ガイドライン・チェックリストを選定し公開予定
2025年07月 認定審査開始予定
※認定審査は有償
2025年10月 NDD認定ガイドラインver2.0 公開予定
2026年04月 ver2.0 制度開始予定
(11月19日Web担当者Forumミーティング秋での講演発表資料より)
今後ますますEC利用者が増え、とくに錯誤を起こしやすい年齢層の利用が拡大していくにつれ、消費者が正しい選択や判断ができるようにEC事業者への規制は強化されていくことが予想されます。
EC事業者の誠実な取り組みは、消費者へのメリットだけでなく、懐疑心を持たれず安心して買い物してもらえるという運営側の評価上昇にもつながることが期待されます。
毎年ECを取り巻く多様なルールが変わっていきますが、変化に負けることなく、2025年が皆様にとって飛躍拡大につながる1年となりますようお祈りいたします!

